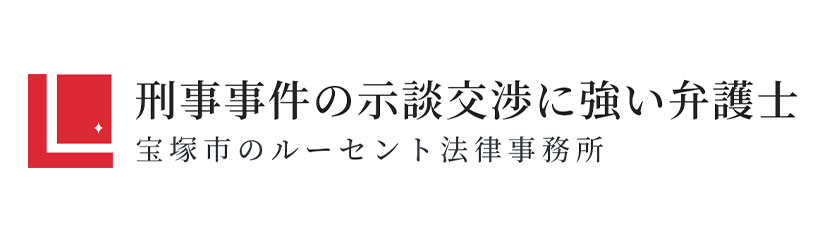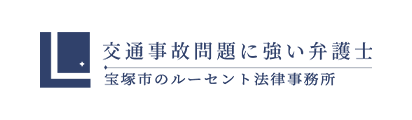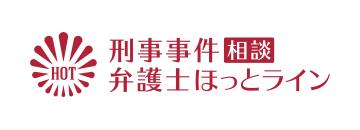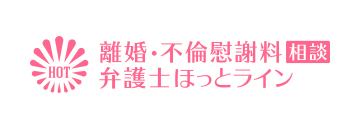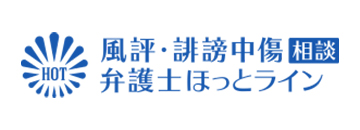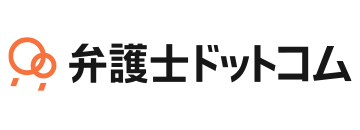はじめに:お子様の健やかな成長のために

離婚を考える際、お子様がいらっしゃるご夫婦にとって、最も重要で、そして最も丁寧な話し合いが必要となるのが「養育費」の問題です。
養育費は、単なる金銭のやり取りではありません。離婚によって離れて暮らすことになっても、親として、お子様に対する扶養義務を果たし、その健やかな成長を支え続けるための、大切な責任の証です。
しかし、その金額や支払い期間を巡って、当事者間で意見が対立し、感情的な争いに発展してしまうことも少なくありません。この記事では、離婚後の養育費に関する基本的な知識(概要、相場、決め方)から、一度決めた後の見直しの可能性まで、知っておくべき全知識を弁護士が分かりやすく解説します。
そもそも「養育費」とは?基本のキ
養育費の概要
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことを指します。
具体的には、食費、住居費、教育費、医療費、被服費、娯楽費などが含まれます。 親は、自身と同程度の生活水準を子どもにも保障する義務(生活保持義務)を負っており、養育費は、この義務を果たすために支払われるものです。
誰が誰に支払う?
原則として、子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと一緒に暮らして実際に監護・養育する親(監護親)に対して支払います。
いつまで支払う?
法律上は「子どもが未成熟子でなくなるまで」とされています。具体的な終期は、離婚時の取り決めで定めますが、一般的には以下のいずれかとするケースが多いです。
20歳まで
成人年齢が18歳に引き下げられましたが、経済的に自立するのは20歳以降という考え方が根強いため、今も主流です。家庭裁判所の実務においても20歳までと判断する場合が多いです。
大学卒業まで
大学進学率の上昇に伴い、増えている取り決めです。ただし、後述するように定め方には注意が必要です。
養育費の金額はどうやって決める?
養育費の金額は、まず当事者間の話し合いで決めますが、その際の基準の一つとなるのが、裁判所が公表している「養育費算定表」です。
裁判所の「養育費算定表」
これは、夫婦双方の収入(給与所得者か自営業者か)と、子どもの人数・年齢に応じて、養育費の標準的な月額が分かるように作られた表です。
家庭裁判所での調停や審判でも、この算定表がたたき台として用いられるため、当事者間の話し合いにおいても、まずこの算定表でご自身のケースの相場を確認することが、公平な金額を決めるための第一歩となります。
算定表以外の考慮要素
算定表はあくまで標準的なケースを想定しています。
お子様が私立学校に通っている、大きな病気や障害で特別な医療費がかかる、といった個別具体的な事情がある場合は、それらの費用を考慮して、算定表の金額に上乗せする形で話し合いが行われます。
また、当事者の年収が極めて大きいケースでも算定表は利用できませんので、個別に計算を行う必要があります。
養育費の決め方と、約束を確実にする方法
- 当事者間の話し合い(協議):まずは夫婦間で、上記の算定表などを参考に話し合います。
- 家庭裁判所での調停: 話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めます。
- 審判・訴訟:調停でも合意に至らない場合は、審判の手続きで、最終的に裁判官が金額を決定します。
合意内容は必ず書面に残す
どのような方法で決めるにせよ、合意した内容は必ず書面に残してください。口約束だけでは、後日「そんな約束はしていない」と言われてしまえば、支払いを強制することが困難になります。
特におすすめなのは「公正証書」
離婚協議書などを、公証役場で「公正証書」として作成することをお勧めします。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、万が一、相手からの支払いが滞った場合に、あらためて裁判を起こすことなく、直ちに相手の給料や預貯金を差し押さえる「強制執行」の手続きが可能です。これは、将来の支払いを確実にするための、非常に強力な担保となります。
一度決めた養育費は、変更できる?
答えは「YES」です。
養育費の取り決めは、その時点での事情を前提としています。
したがって、取り決めをした後、当事者のどちらかに予測できなかった大きな事情の変更があった場合には、養育費の増額または減額を求めることができます。
増額が認められるケース
- 支払う側の収入が大幅に増加した。
- 受け取る側の収入が、病気やリストラで大幅に減少した。
- 子どもの年齢が上がり、必要な養育費が大幅に増えた。
- 子どもが大きな病気や怪我をし、高額な医療費が必要になった。
減額が認められるケース
- 支払う側の収入が、病気やリストラで大幅に減少した。
- 支払う側が再婚し、扶養すべき子どもが生まれた。
- 受け取る側が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした。
(この場合、再婚相手が第一次的な扶養義務者となるため、養育費が大幅に減額または免除される可能性が高いです。) - 受け取る側が再婚し、世帯収入が大きく増加した。
(養子縁組をしていなくても、減額の理由となり得ます。)
これらの増減額を求める手続きも、基本的には最初に養育費を決める手続き(話し合い→調停→審判)と同じ流れで進めます。
養育費Q&A
養育費に関して、よくご相談いただく内容をQ&A形式でまとめました。
Q:養育費の終期を「大学卒業まで」と決めようと思いますが問題はありませんか?
A:トラブルの原因となる可能性があり原則としておすすめできません。
「大学卒業」の具体的な年月日が明確ではないからです。たとえば、浪人や留年によって大学卒業が遅れた場合、支払う側の負担は大きく増えてしまいます。受け取る側においても、終期が明確ではない約束では強制執行ができない場合があります。終期は具体的な年月日で定めていただくことが望ましいです。
Q:公正証書を作成しておけば養育費の支払は確実ですか?
A:公正証書を作成しておけば絶対にそのとおり支払が得られるというものではありません。
公正証書はあくまでも、強制執行が可能となるチケットに過ぎません。
合意後の事情の変更によって養育費が減額または0になる場合もあるため、公正証書を作成しておけば絶対にそのとおり支払が得られるというものではありません。また、公証役場は通常、公正証書の具体的な内容の適否について踏み込むことはありません。
公証人は当事者が持ち込んだ合意内容を公正証書としてまとめるだけです。公正証書の内容が適切かどうかは個別に弁護士のチェックを経ることや最初から弁護士に作成を依頼されることが望ましいです。
当事務所でご依頼をお預かりしている事件でも、「弁護士が関与せず当事者間のみで作成した公正証書の内容に不備があり、養育費請求のために結局裁判が必要になった」ケースが散見されます。
Q:子どものことを考え、離婚慰謝料を支払ってもらう代わりに、養育費を相場より高い額で合意しようと思います
A:非常に危険です。
養育費は一度決めたからといって、未来永劫その金額の支払が保障されているものではありません。
離婚後に事情の変更があれば、減額や0になることが当然想定されます。過大な養育費であれば減額の余地はなおさら大きくなります。
慰謝料(や財産分与)を養育費に含めて考えるのは全くおすすめできません。養育費は養育費、慰謝料は慰謝料と分けて合意する必要があります。
お子様のために、適正で、確実な取り決めを

養育費は、お子様が健やかに成長していくための権利です。離婚する際には、感情的にならず、お子様の未来のために、双方が納得できる形で、適正かつ確実な取り決めを行うことが何よりも大切です。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、離婚に伴う養育費の問題に豊富な経験がございます。「相手が養育費の話し合いに応じてくれない」「提示された金額が妥当か知りたい」「事情が変わったので金額を見直したい」など、養育費に関するお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。お子様とあなたの未来のために、私たちが法的な専門家として、最善の解決策を一緒に考えます。