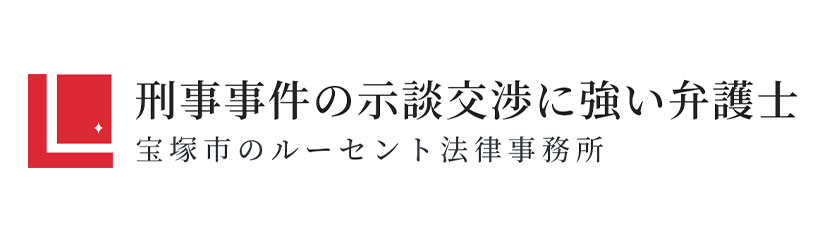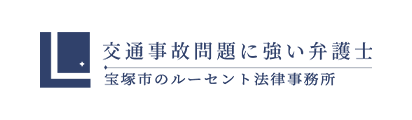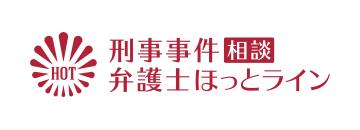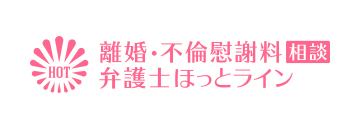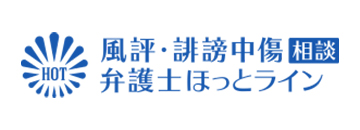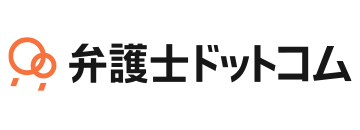はじめに:「一度決めた養育費」といっても、絶対ではない

離婚の際に、公正証書や調停調書などで、お子様のための養育費の金額を取り決めたことと思います。「一度サインしたのだから、この金額をずっと払い続けなければならない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、養育費の取り決めは、その時点での双方の収入やお子様の年齢を基に決定されたものです。その後の長い年月の間には、ご自身の状況や、お子様を監護している相手方(親権者)の状況に、大きな変化が生じることもあります。
日本の法律では、そのような「事情の変更」があった場合には、一度決めた養育費の金額であっても、増額または減額を求めることが認められています。
この記事では、どのような場合に養育費の減額請求が可能なのか、特に近年増えている「相手方の再婚」というケースを中心に、その手続きと、弁護士に相談するメリットについて分かりやすく解説します。
養育費が見直される基本ルール「事情変更の原則」
養育費の金額は、取り決めをした時点では予測できなかった、やむを得ない事情の変更があった場合に、見直すことができます。これを法律の世界では「事情変更の原則」といいます。
具体的に、養育費の減額が認められやすいのは、以下のようなケースです。
支払う側(義務者)の事情
- 会社の倒産やリストラによる失業、転職などで収入が大幅に減少した。
- 病気やケガで長期間働けなくなり、収入が減少した。
- ご自身が再婚し、扶養すべき新たな子が生まれた。
受け取る側(権利者)の事情
- 相手方の収入が、取り決め時よりも大幅に増加した。
- 相手方が再婚した。
これらの事情が生じたからといって、勝手に支払額を減らしたり、支払いを止めたりすることは許されません。
必ず、正式な手続きを踏む必要があります。
相手方(親権者)が再婚した場合
相手方が再婚した場合は、養育費の減額を主張できる、極めて重要な「事情の変更」にあたります。
この場合、さらに「お子様が、再婚相手と養子縁組をしたかどうか」で、状況が大きく変わります。
【ケース1】相手が再婚し、子が再婚相手と「養子縁組」した場合
法的な状況
お子様が再婚相手と普通養子縁組をすると、法律上、再婚相手(養親)が、お子様に対する第一次的な扶養義務者となります。つまり、お子様を扶養するメインの責任者は、再婚相手になるのです。
一方で、あなた(実親)の扶養義務がなくなるわけではありませんが、その立場は第二次的なものに後退します。
養育費への影響
この場合、まずは第一次的な扶養義務者である再婚相手がお子様を扶養すべき、ということになります。
そのため、あなたからの養育費は、大幅に減額される、あるいは、場合によってはゼロとなる可能性が非常に高いです。
これは、減額請求が認められる最も強力な理由の一つです。
【ケース2】相手が再婚したが、養子縁組は「していない」場合
法的な状況
養子縁組をしていない場合、あなた(実親)の扶養義務は第一次的なままです。
しかし、相手方の再婚により、世帯全体の収入が増加し、生活に余裕が生まれていると考えられます。
養育費への影響
相手方世帯の収入が増えた分、あなたがお子様のために負担すべき金額は、以前よりも少なくて済む、と評価される可能性があります。
したがって、この場合も、養育費が減額される可能性は十分にあります。
ただし、養子縁組をしたケースに比べると、減額の幅は小さくなる傾向にあります。
養育費の減額を求める手続きの流れ
1.まずは当事者間での話し合い
まずは、相手方に対し、事情の変更があったこと、そして養育費の減額を希望することを伝え、話し合いを試みます。
ここで双方が合意できれば、新たな条件を記した合意書(できれば公正証書)を作成するのが望ましいです。
2.話し合いがまとまらなければ「養育費減額請求調停」
当事者間の話し合いで合意できない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。
調停では、調停委員(裁判官と民間の有識者)が中立な立場で間に入り、双方の事情を聞きながら、合意による解決を目指します。
3.調停不成立なら「審判」へ
調停でも合意に至らない場合は、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行します。
審判では、裁判官が双方から提出された資料や主張に基づき、法的な観点から、養育費を減額すべきか、減額するならいくらが妥当かを判断し、決定を下します。
養育費の減額請求を弁護士に相談すべき理由
養育費の減額は、お子様の生活にも関わるデリケートな問題です。感情的な対立も生まれやすく、当事者同士での冷静な話し合いは非常に困難なことが多いです。このような時こそ、弁護士にご相談ください。
1.そもそも減額請求が法的に可能か、的確に判断するため
あなたの状況が、法的に「事情の変更」として認められ、減額請求が通る見込みがあるのかどうか、専門的な観点から的確に判断します。また、再婚や養子縁組・収入の増減について適切に主張・立証するための証拠収集が欠かせません。
2.感情的になりがちな相手方との交渉を代理するため
弁護士があなたの代理人として、冷静かつ論理的に相手方と交渉します。「お金を払いたくないだけだろう」といった感情的な非難を避け、法的な根拠に基づいて、減額の必要性を説得的に伝えます。
3.家庭裁判所での調停・審判手続きを有利に進めるため
調停や審判では、ご自身の収入状況や相手方の状況などを、客観的な資料(給与明細、確定申告書など)に基づいて主張・立証する必要があります。弁護士は、これらの手続きを代理し、あなたに有利な結論が得られるよう全力を尽くします。
4.法的な根拠に基づき、適正な減額後の養育費を算出するため
裁判所が用いる「養育費算定表」などの基準に基づき、現在の状況における適正な養育費額を算出し、具体的な減額目標を設定して交渉に臨みます。特殊な事例では算定表に基づいた算定ができない・不適切な結果となってしまう場合があり、そのような場合は算定表の根拠となっている計算方法を用いて細かく計算を行います。
子どものためにも、現状に即した公平な負担を

養育費の減額請求は、決して「子どものための支払いを放棄する」ということではありません。
それは、ご自身の生活を維持し、安定して養育費を支払い続けるためにも、そして、変化したお互いの状況に合わせて、公平な負担に見直すための、正当な権利です。
無理な支払いを続け、ご自身の生活が破綻してしまっては、結果的にお子様のためにもなりません。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、離婚後の養育費に関する様々なご相談に対応しております。「自分の場合、養育費は減額できるだろうか」「相手が再婚したが、どう切り出せばいいかわからない」など、お悩みのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。