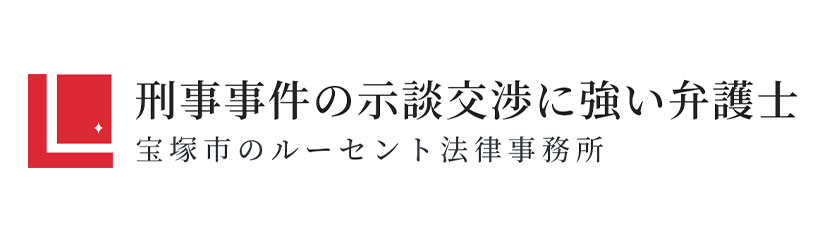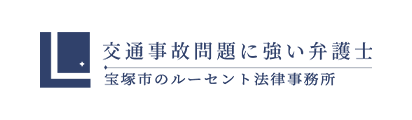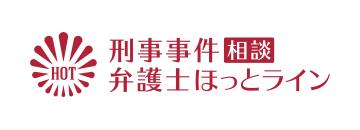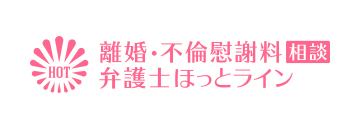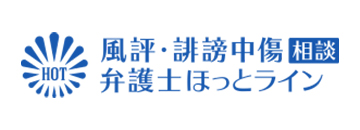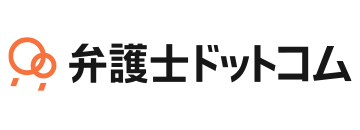はじめに:マイホームの夢を叶える「ペアローン」

「夫婦共働きで収入を合算し、希望のマイホームを手に入れたい」
「一人分の収入では住宅ローンの審査が通らないが、二人なら借りられる」
このような希望を叶える方法の一つとして、金融機関が提供する「ペアローン」があります。夫婦やパートナーがそれぞれローンを組むことで、一人で借りるよりも高額な融資を受けられ、マイホームの夢を実現しやすくなるため、利用される方が増えています。
しかし、このペアローンは、夫婦関係が円満なうちは大きなメリットがある一方で、万が一、離婚することになった際には、非常に複雑で解決が難しい問題を引き起こす大きな落とし穴となり得ます。
この記事では、ペアローンの基本的な仕組みと、離婚時に直面するリスク、そしてその解決のために弁護士ができることについて解説します。
「ペアローン」の仕組みとは?
ペアローンとは、一つの不動産(マイホーム)を購入するために、夫婦(またはパートナー)がそれぞれ住宅ローンを契約する方法です。
- 2本のローン契約
夫が主債務者のローンA、妻が主債務者のローンBというように、それぞれが独立したローン契約を結びます。 - お互いが連帯保証人
夫は妻のローンBの連帯保証人となり、妻は夫のローンAの連帯保証人になるのが一般的です。 - 共有名義
購入した不動産は、ローンや負担した頭金の割合などに応じて、夫婦の共有名義となります。 - 住宅ローン控除
夫婦それぞれがローンを組んでいるため、二人とも住宅ローン控除(減税)の適用を受けられるメリットがあります。
このように、ペアローンは、より多くの資金を借り入れ、協力してマイホームを所有するための有効な手段です。
しかし、離婚時には大きな障害に…ペアローンの落とし穴
問題は、夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に発生します。
離婚したからといって、住宅ローンの返済義務や、お互いの連帯保証人の立場が自動的になくなるわけでは全くありません。
「私たちはもう夫婦ではないから関係ない」という理屈は、金融機関には通用しないのです。離婚後も、それぞれが自分のローンの返済を続け、かつ、元配偶者のローンの連帯保証人であり続けるという、非常に不安定でリスクの高い状態が残ります。
ペアローン住宅の離婚時の主な問題点と解決策
離婚時にペアローン付きの不動産をどうするか、主な選択肢とそれぞれの問題点は以下の通りです。
1. 家を売却する場合の問題点(オーバーローン/アンダーローン)
最も望ましいのは、家を売却した代金で夫婦双方のローンを完済し、残った利益を財産分与することです(アンダーローンの状態)。売却での解決ができないかをまずご検討いただくべきです。
問題は、家の売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態です。
この場合、売却してもローンを完済できず、不足分を自己資金で補填しなければなりません。離婚に際して、そのようなまとまった資金を捻出するのは非常に困難な場合が多く、「売りたくても売れない」という状況に陥ります。
2. どちらかが住み続ける場合の問題点
例えば、妻と子が家に住み続け、夫が出ていく場合を想定します。この場合、理想は妻が夫のローン分も引き受けて返済することですが、妻一人の収入で2本のローンを返済していくのは現実的ではありません。
夫が自分のローン分を支払い続けるとしても、妻が自分のローンを滞納すれば、連帯保証人である夫に請求や強制執行が来ます。逆もまた然りです。元配偶者の経済状況に、自分の信用情報や経済的負担が左右されるリスクを負い続けることになります。
金融機関にローンの名義を一人にまとめる(借り換える)相談をしていただくことも検討していただくべきです。住み続ける方の配偶者に十分な収入がある場合や、返済が進んでいて残高が多くない場合には審査がとおりローンの借り換えの上、名義を単独名義に変更することができます。
なお、単に連帯保証人を外してほしいという相談については、金融機関が安易に連帯保証人を外してくれることはまずありません。
3. 賃貸に出す場合の問題点
「家を賃貸に出し、その家賃収入でローンを返済する」という方法も考えられますが、ほとんどの住宅ローンは「契約者本人が居住すること」が融資の条件となっています。
金融機関に無断で賃貸に出すことは契約違反にあたり、最悪の場合、ローンの一括返済を求められるリスクがあります。
共有名義のリスクとは?
そもそも、ペアローンによって生じる「共有名義」の状態そのものが、離婚後のトラブルの大きな原因となります。
共有名義の不動産は、売却するにも、賃貸に出すにも、あるいは大規模なリフォームをするにも、共有者全員(つまり元配偶者)の同意が必要です。
離婚後、関係が悪化した元配偶者と、不動産の処分について冷静に話し合い、協力して手続きを進めることは、精神的にも非常に困難な作業です。相手方が非協力的であれば、不動産は「塩漬け」状態になってしまいます。
離婚の場面に限らず、不動産を共有名義にするということは一般的におすすめできるものではありません。これから借り入れを予定されている方については、本当に共有名義にしなければならないのかを立ち止まって検討してください。
ペアローン離婚こそ、弁護士への相談が不可欠な理由
ペアローンが絡む離婚は、財産分与の中でも最も複雑で解決が難しい類型の一つです。当事者同士での解決は極めて困難であり、感情的な対立を深めるだけになりかねません。このような状況でこそ、弁護士にご相談いただくメリットは非常に大きいと言えます。
1.複雑な財産・債務関係の整理
弁護士は、不動産の価値(査定)、双方のローン残高、連帯保証の関係などを法的に整理し、問題の全体像を把握します。
2.冷静かつ有利な交渉の代理
弁護士があなたの代理人として、元配偶者と冷静に交渉します。感情的な対立を避け、法的な根拠に基づき、売却、名義変更、代償金の支払いなど、あなたにとって最も有利で現実的な解決策を粘り強く模索します。
3.金融機関との交渉・調整
簡単ではありませんが、弁護士が金融機関と交渉し、売却(任意売却)の許可や、条件変更の可能性を探るなど、専門家として調整を図ります。
4.将来の紛争を防ぐ離婚協議書・公正証書の作成
話し合いで合意した内容は、必ず法的に有効な書面(離婚協議書や、より強制力の強い公正証書)に残す必要があります。
弁護士は、不動産の処分方法、ローンや連帯保証債務の負担、養育費や慰謝料など、全ての取り決めを網羅し、将来のトラブルを防ぐための、合意書を作成します。
5.実現可能な解決策の提示
「売却」「住み続ける」など、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを具体的に説明し、あなたの状況に合わせた最も現実的で、実行可能な解決策を一緒に考えます。
安易な判断は禁物。まずは専門家にご相談を

ペアローンは、マイホームの夢を後押ししてくれる便利な仕組みですが、その裏には、関係性が変わったときに大きなリスクを伴うことを理解しておく必要があります。
もし、あなたがペアローンを組んでおり、離婚を考えている、あるいは既に相手方から離婚を切り出されているという状況であれば、安易に「自分が住み続ける」「ローンは払い続ける」などと約束してしまう前に、必ず弁護士にご相談ください。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、このような複雑な財産分与が絡む離婚問題を数多く解決してまいりました。
初回のご相談は無料です。あなたの状況を丁寧にお伺いし、専門家として最善の解決への道筋を示します。一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。