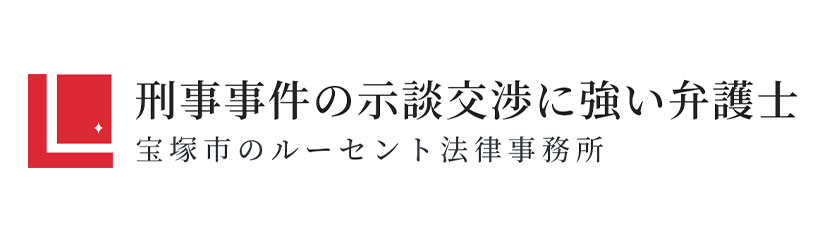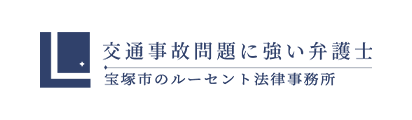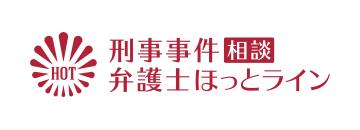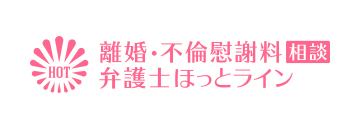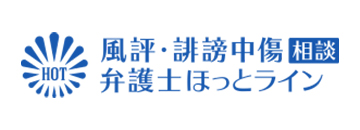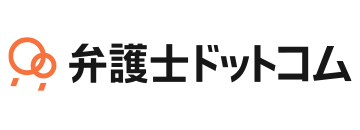はじめに:「おひとりさま」や内縁関係、ご自身の財産はどうなる?

「自分には配偶者も子もいないし、両親や兄弟も既に亡くなっている。自分の財産は一体どうなるのだろう?」
「長年連れ添った内縁の妻(夫)がいるが、法律上の夫婦ではない。私が亡くなったら、彼女(彼)に財産を残せるだろうか?」
「親族ではないが、長年身の回りのお世話をしてくれた恩人に、感謝の気持ちとして財産を渡したい」
このように、法律で定められた相続人(法定相続人)がいない方や、法定相続人以外の大切な人に財産を残したいと考える方は、少なくありません。ですが、ご自身の意思で財産の行き先を決めておかなければ、その想いは実現されない可能性があります。
この記事では、法定相続人がいない場合に財産がどうなるのか、そして、内縁の配偶者やお世話になった方へ確実に財産を残すための最も望ましい方法について、分かりやすく解説します。
遺言書も法定相続人もいない場合、財産は最終的に「国」のものに
まず、法律上のルールを知っておくことが重要です。
遺言書がなく、かつ法定相続人(※1)が一人もいない場合、最終的にその方の財産は「国庫」に帰属します。つまり、国のものになります。
たとえ長年連れ添った内縁の配偶者や、身を粉にして介護をしてくれたお世話になった方がいても、法律上の相続人ではないため、自動的に財産を受け取る権利はありません。
※1 法定相続人とは?
法律で定められた相続人のこと。配偶者は常に相続人となり、それに加えて以下の順位で相続権が移ります。
第1順位:子(子が既に亡くなっている場合は孫)
第2順位:親(親が既に亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪)
この第3順位まで誰もいない場合を、「法定相続人がいない」状態といいます。
例外的な制度「特別縁故者」とは? しかし、多くのハードルが…
「では、内縁の妻やお世話になった人は、全く財産を受け取れないのか?」というと、全く道がないわけではありません。「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」(※2)という制度があります。
※2 特別縁故者とは?
法定相続人ではないものの、故人と特別な縁故(つながり)があった人のことです。法律では、主に以下の3つのケースが挙げられています。
1.故人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者など)
2.故人の療養看護に努めた者(長年にわたり献身的に介護した親族や友人など)
3.その他、故人と特別の縁故があった者
特別縁故者として財産を受け取るための手続きと問題点
この制度には、以下のような多くのハードルがあり、確実な方法とは言えません。
手続きが非常に複雑で、時間がかかる
- まず、家庭裁判所に「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」を選任してもらう申立てが必要です。
- 選任された清算人が、故人の財産や負債を調査し、債権者への支払いなどを行います。
- その後、本当に相続人がいないかを探すための公告手続きなどが行われます。
- これらの手続きが全て終わり、なお財産が残っている場合に、ようやく特別縁故者として財産分与を求める申立てができます。この一連の手続きには、通常1年以上の長い時間がかかります。
必ず認められるとは限らない
申立てをしても、特別縁故者として認めるか、また、どれくらいの財産を分与するかは、最終的に家庭裁判所が判断します。
献身的な貢献があったとしても、必ずしも望む結果が得られるとは限りません。
申立人に立証責任がある
申立てをする人が、自ら故人との間に「特別な縁故」があったことを、証拠をもって証明しなければなりません。
このように、特別縁故者制度は、あくまで相続人がいない場合の例外的な救済制度であり、生前にご自身の意思で財産を誰かに残すための、確実な方法とは言えないのです。
最も確実で望ましい方法、それは「遺言書」の作成です
内縁の配偶者やお世話になった方、あるいは特定の団体(寄付)などに、ご自身の財産を「確実に」「あなたの意思通りに」残すための最も有効で望ましい方法。
それが「遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)」の作成です。
遺言書があれば、
- 法定相続のルールに縛られず、財産を渡したい相手を自由に指定できます。(これを「遺贈(いぞう)」といいます。)
- 複雑な特別縁故者の手続きを経る必要がありません。
- あなたの最後の想いを、明確な形で残すことができます。
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は手軽ですが、方式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。
一方、法律の専門家である弁護士が作成に関与した公正証書遺言は、無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため、最も安全で確実な方法としてお勧めできます。
なぜ弁護士に遺言書作成を依頼すべきなのか
遺言書の作成は、あなたの人生の総仕上げともいえる重要な法律行為です。後日のトラブルを避け、あなたの想いを確実に実現するために、弁護士にご相談・ご依頼いただくことには大きなメリットがあります。
- 法的に有効な遺言を作成するため
自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言を作成する際にも、法律の専門家である弁護士が関与することで、方式の不備や内容の曖昧さをなくし、法的に有効な遺言書を作成できます。 - あなたの想いを正確に形にするため
弁護士は、あなたの「誰に、何を、どのように残したいか」という想いを丁寧にヒアリングし、それを最も適切かつ誤解の生じない法的な表現で遺言書に落とし込みます。 - 信頼できる遺言執行者を指定するため
遺言の内容を実現する手続きは、意外と煩雑です。特に、相続人でない方が財産を受け取る場合、手続きで困難に直面することもあります。作成と併せて弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、死後の手続き全般をスムーズかつ確実に進めることができ、財産を受け取る方の負担を大きく軽減できます。 - 将来の不安をなくし、安心を得るため
専門家と共に、法的に有効で、ご自身の意思が明確に反映された遺言書を作成することで、「自分の亡き後、大切なあの人は大丈夫だろうか」という将来への不安が解消され、大きな安心感を得ることができます。
あなたの最後の想いを、大切な人へ確実に届けるために

法定相続人がいない方、あるいは法定相続人以外の大切な人に財産を残したいと考える方にとって、遺言書の作成は「いつかやること」ではなく、「元気なうちに必ずやっておくべきこと」です。
それは、あなたの想いを実現する唯一の道であり、残される方への最後の、そして最大の思いやりです。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域の皆様の相続・遺言に関するお悩みに、親身に対応しております。
「何から始めたらいいかわからない」「内縁の妻に確実に財産を残したい」など、あなたの具体的なご希望や状況をお聞かせください。
初回相談は無料です。あなたの想いを法的に有効な形で残し、大切な方へと確実に届けるためのお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。