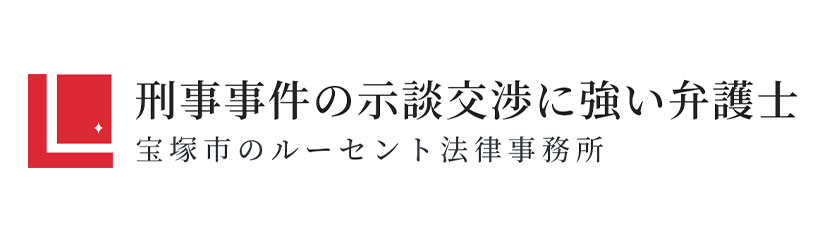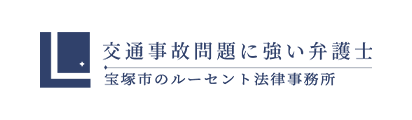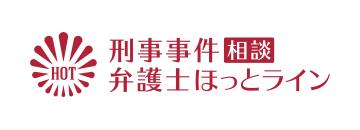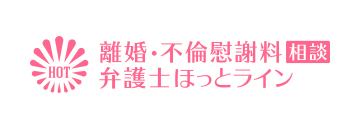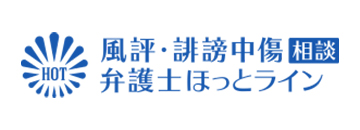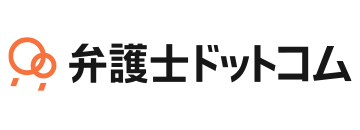はじめに:遺留分とは?

相続が発生した際、遺言書があれば遺言が優先されます。
しかし、遺言書によって家族のうち1人だけが遺産を相続したり、家族ではない恋人や友人に遺産をすべて遺贈されたりしてしまうと、残された親族が生活できなくなってしまうおそれがあります。
そのため、亡くなった方と一定の関係性にある家族を守るために法律で定められているのが「遺留分」です。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは
法定相続分は、法定相続人が亡くなった方の財産を受け取れる、民法で定められた割合です。ただし、法定相続分は目安であり強制されるものではありません。
遺言書があれば、法定相続分よりも遺言にかかれた割合が優先されます。また、相続人全員が同意すれば遺産を自由に分けることができます。
法定相続人となる方は状況に応じて異なりますが、配偶者・子ども・親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪などです。
遺留分とは
遺留分は、遺留分が認められる相続人に対して最低限保障される遺産取得割合です。相続人や相続分は、基本的には遺言や話し合いによって自由に決めることができます。しかし、それによって身近な方が損をしたり、親族が生活できなくなったりすることを避けるために法定されています。
遺留分が認められる相続人は、配偶者、子・孫・ひ孫などの直系卑属、父母・祖父母・曾祖父母などの直系尊属です。
これらの方々は遺言書に受取人として名前が書かれていない場合でも、遺留分を受け取る権利を主張することができます。ただし、遺留分を主張するかどうかは本人の自由であり受け取らなくても問題はありません。
遺留分を計算する方法
遺留分の割合
遺留分の割合は次のように決まっています。
<配偶者がいる場合>
| 相続人の構成 | 相続人 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | 2分の1 |
| 配偶者と子供 | 配偶者 | 4分の1 |
| 子 | 4分の1 | |
| 配偶者と父母(祖父、祖母) | 配偶者 | 3分の1 |
| 父母 (祖父、祖母) | 6分の1 | |
| 配偶者と 兄弟姉妹 | 配偶者 | 2分の1 |
| 兄弟姉妹 | なし |
<配偶者がいない場合>
| 相続人の構成 | 相続人 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 子のみ | 子 | 2分の1 |
| 父母(祖父、祖母) のみ | 父母 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹 | なし |
遺留分の計算方法
遺留分の割合がわかれば、金額は次の式で計算して求めることができます。
相続財産総額(相続財産+生前贈与等-債務)×遺留分割合=遺留分
気をつけなければならないのは、相続財産の総額を求める際に被相続人が亡くなる前の生前贈与や特別受益などを合算しなければならないことです。
また、被相続人に借金があった場合は、総額から差し引いたうえで計算をすることになります。
まとめ

遺留分は、その権利を持つ相続人が最低限受け取ることができる相続分です。
配偶者や子どもは遺留分権利者なので、もしも、最低限の財産も受け取れないような状況になっているなら、遺留分を侵害されているのかもしれません。そのようなときは、遺留分の請求を進めることで財産を取り戻すことが可能です。
基本的に遺留分はお金で清算するものなので、たとえすでに不動産が誰かの手に渡っていたとしても、遺留分はお金に換えて支払ってもらうことができます。
遺留分の計算や主張を自分でおこなうのは簡単なことではありません。
当事務所では、遺留分の問題を含む相続全般のサポートをしています。権利者が受け取るべき財産をきちんと受け取れるよう、お手伝いいたします。
自分が財産を受け取れない遺言書が見つかり困っている場合や、遺留分を侵害されているかもしれないと不安な方は、宝塚市のルーセント法律事務所までご連絡ください。