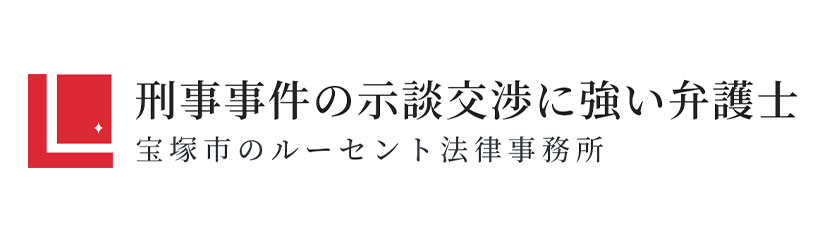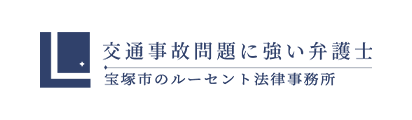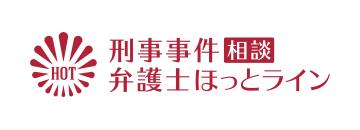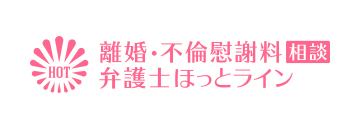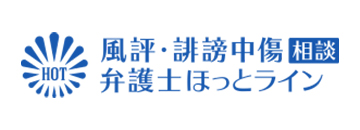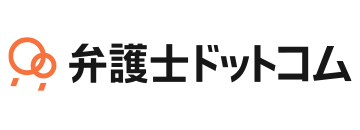はじめに
相続は、多くの方にとって人生で何度もおこなう手続きではありません。耳慣れない言葉も多く、難しく感じてしまう方もいるでしょう。なかでも『承継人』と『相続人』は、言葉は似ていますが意味が異なり、混同しやすいものです。
今回は、承継人と相続人の違いや、違いを踏まえた相続時の準備と注意点を解説します。
承継人と相続人の違い
承継人とは
承継人とは、簡単に言うと、誰か(被承継人)から財産・権利・義務などを引き継ぐ『すべての人』を指す広い言葉です。実は、後で説明する『相続人』も、この承継人の一種に含まれます。
相続も、財産などを引き継ぐ行為であり、承継のうちの一種です。承継の方法には、相続以外にも、売買・会社の合併や分割・事業譲渡などがあります。
承継人には、一般承継人と特定承継人の2種類があります。主な違いは次のとおりです。
- 一般承継人
一般承継人とは、被承継人の権利や義務をすべてまとめて(包括的に)引き継ぐ人のことです。相続においては、法定相続人や、遺言で『全財産の〇分の〇を相続させる』といった形で包括的に遺贈を受けた人などがこれにあたります。
- 特定承継人
特定承継人とは、売買や贈与などによって、特定の財産や権利だけを個別に引き継ぐ人のことです。相続においては、遺言で『この土地を〇〇に相続させる』といった形で、特定の財産を指定して遺贈を受けた人(特定受遺者)などがこれにあたります。
相続人とは
相続は承継の一種です。相続とは、亡くなった方の財産についての権利義務を引き継ぐ手続きであり、民法に規定されています。
そして、この亡くなった方の財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。
相続時のための準備
相続時のための準備が必要な理由
相続トラブルを防ぐために準備が重要です。
特に遺言は重要で、その書き方によって、財産の引き継ぎ方が変わってきます。
具体的には、遺産の分け方を相続人の話し合いに委ねるような指定(包括的な指定)もあれば、特定の財産を特定の人に引き継がせる指定(特定的な指定)もあります。
どちらが良いかは状況によりますが、意図しない相続トラブルを避けるためにも、ご自身の希望に合った形で準備しておくことが大切です。相続時、これらの引き継ぎ方によってケンカやトラブルに発展することも少なくありません。
相続時のためにできる準備
相続の準備として重要なのが、遺言です。遺言の書き方によって、相続手続きも異なります。
- 包括的な指定(一般承継につながる遺言)の場合
被相続人が相続分の指定をし、具体的な遺産分割の方法は相続人同士の話し合いで決めることになります。
例えば、次のような遺言です。 「妻の相続分を3分の2、長男の相続分を3分の1とする」
- 特定的な指定(特定承継につながる遺言)の場合
被相続人がどの財産を誰に相続させるかを指定し、相続人は遺産分割をせずに特定の財産をそれぞれ受け継ぎます。
例えば、次のような遺言です。 「土地Aを妻に、家屋Bを長男に相続させる」
相続手続きで押さえておきたい注意点
相続手続きには期限がある
相続手続きには期限があります。なかでも以下の手続きの期限は重要ですので注意しましょう。
- 相続放棄・限定承認の申述(3か月)
- 亡くなった方の所得税申告(準確定申告)(4か月)
- 相続税の申告と納付(10か月)
遺言があっても遺留分が優先する
配偶者、子ども(やその代襲相続人)、親などの直系尊属には、法律で最低限保障されている遺産の取り分があります。
これを「遺留分」といいます。
たとえ遺言書で「全財産を特定の一人に」と書いたとしても、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害された相続人は、その侵害額に相当する金銭を請求(遺留分侵害額請求)する権利があります。
まとめ
相続は、ご家族の状況によっては複雑な準備や話し合いが必要になる手続きです。亡くなったときに相続人が揉めてしまわないよう、事前準備をしておくことが大切です。
遺言書の作成など、相続の準備をお考えの方は、ルーセント法律事務所へいつでもご相談ください。みなさまが納得できる相続がおこなわれるよう、全力でサポートいたします。