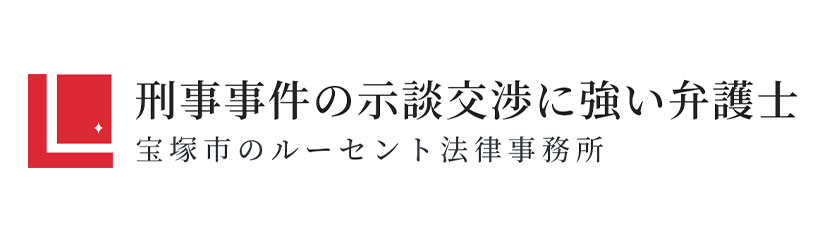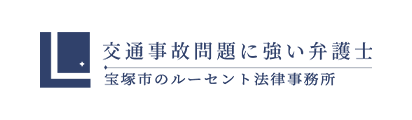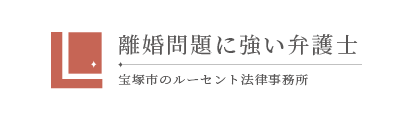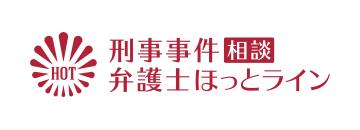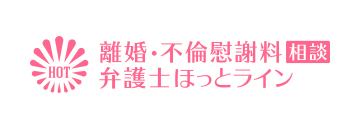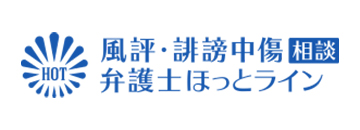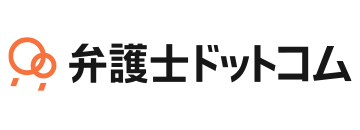はじめに
配偶者や親族が亡くなって相続が発生すると、さまざまな手続きをしなければなりません。特に、不動産を相続する場合は、相続登記という複雑な手続きも必要となります。
以下では、不動産の相続について、詳しくご説明していきます。
不動産の相続に必要な手続き
不動産の相続のための手続きは、次のような流れになります。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定させる
- 財産を特定する
- 財産目録を作成する
- 遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
- 相続登記をする
- 相続税の申告と納税をする
相続が発生したら、まずは遺言書を探してください。遺言書があった場合、原則としてその内容どおりに遺産が分けられます。遺言書の有無は相続において極めて重要な要素です。
同時に、相続人を確定させる必要があります。市役所においてお亡くなりになった方が生まれてから死亡するまでの間の戸籍謄本を全て取得し、相続人となる人を洗い出してください。
この作業には従前かなりの手間隙が掛かりましたが、近時では広域交付制度の開始により一箇所の市役所で全て取得することができます。広域交付制度についてはこちらの記事をご参考にされてください。
次に、亡くなった方の財産を特定して、財産目録を作成してください。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めます。決めた内容は、遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名押印を行います。
遺産分割協議書は相続登記やその他の手続の際にも利用するため、作成はほぼ必須とお考えください。後々遺産分割の内容について紛争にならないためにも、適切に作成を行っておくことが必要です。
不動産を相続する方が決まったら、相続登記の申請を行います。
相続税の申告が必要な場合、10ヵ月以内に申告を行う必要があります。
不動産を相続する方法
相続財産の中に不動産がある場合、どのように分けるのかを決める必要があります。以下は典型的な分け方をまとめています。
1.代償分割
代償分割とは、財産を多く相続する方が少ない方に代償金を支払う方法です。例えば、相続人が2人・財産が評価額5,000万円の不動産だけとすると、相続人の1人が不動産を相続して、他方に対して2,500万円の代償金を支払います。
代償金の金額は、必ずしも均等である必要はありません。お互いに納得できた金額で合意することが可能です。
2.換価分割
換価分割とは、相続した不動産を売却し、現金化してから分けることです。
例えば、相続人が2人・相続した不動産の売却価格が5,000万円だった場合は、それぞれが2,500万円を受け取ります。
実際のケースでは、仲介手数料等売却に要する実費を差し引いた上で分割をするケースが多いです。
3.共有名義
共有名義は、相続人が複数名いる際、相続人が全員で不動産を共有して所有する方法です。各相続人が所有する割合を設定して、持分割合として相続登記をすることができます。
ただし、1つの不動産を複数の相続人が共有名義で相続するのは、あまりおすすめできません。持ち分が細かくなることで管理や処分の際に支障が生じ、将来的にトラブルとなることが予想されます。
よほどの理由がなければ、不動産は単独名義にしておくべきです。
不動産の相続に必要な書類
相続登記には、さまざまな書類が必要です。通常必要となる書類は以下のとおりです。
- 相続登記申請書
- 登記事項証明書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票と戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 所有者となる方の住民票
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 遺言書
- 相続関係説明図
- 収入印紙・登録免許税印紙納付台紙
まとめ
不動産の相続について見てきました。
相続人間で分割の方法が決まったとしても、その後の相続登記には高度な専門性があり相続人の方がご自身で対応をされるのは困難です。
ルーセント法律事務所では、司法書士や不動産鑑定士とも連携の上、遺産分割の手続や相続登記の手続を対応させていただいております。
「どのように分けたらいいのかわからない」といった遺産分割方法のご相談から、相続登記のご依頼まで幅広くご対応可能です。
相続のお手続きでお困りの際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。