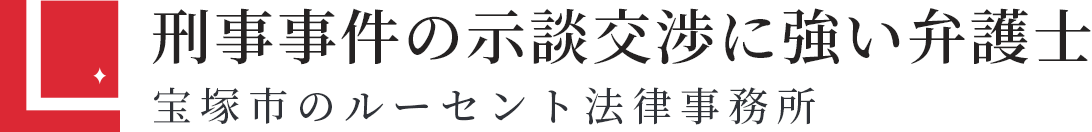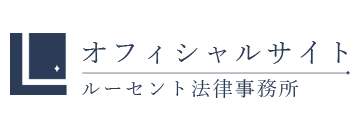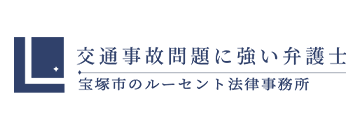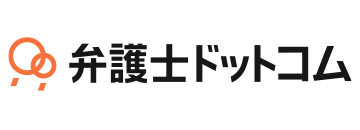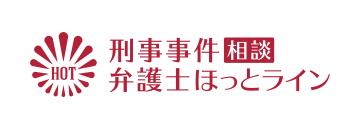はじめに:少年事件は「罰を与える」ことだけが目的ではありません

もしあなたのお子様(原則として20歳未満)が、万引き、喧嘩(傷害)、バイクの窃盗、あるいはそれ以上の重大な事件に関与してしまった、あるいはその疑いをかけられてしまったら…。
ご家族としては、計り知れない不安と混乱の中にいらっしゃることと思います。「これからどうなるのだろう」「学校や将来への影響は?」「前科がついてしまうのか?」など、心配は尽きないでしょう。
まず知っていただきたいのは、日本の少年事件の手続き(少年法)は、大人(成人)の刑事事件とは目的や流れが大きく異なるということです。
大人の刑事事件が「犯した罪に対して刑罰を与えること」に主眼が置かれるのに対し、少年事件は、その少年がなぜ非行(犯罪やそれに類する行為)に至ったのかという背景や原因を探り、少年の健全な成長を助け、更生(立ち直り)を促すこと(=保護主義・教育主義)を主な目的としています。
そのため、手続きは主に家庭裁判所が中心となって進められ、成人事件とは異なる特別な配慮がなされます。ここでは、少年事件の一般的な手続きの流れを分かりやすく解説します。
1. 事件発生から警察の捜査まで
事件が発生し、少年が関与した疑いがある場合、まずは警察が捜査を行います。
これは成人の場合と似ていますが、少年であっても逮捕されたり、その後勾留されたりする可能性はあります(ただし、その要件や手続きには少年法独自の配慮があります)。警察は、少年や関係者から事情を聞き、証拠を集めます。
2. 原則として全ての事件が家庭裁判所へ(全件送致主義)
捜査の結果、警察や検察官が「犯罪の疑いがある」または「家庭裁判所の審判にかけるのが相当」と判断した場合、原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
成人の場合は検察官が起訴・不起訴を判断しますが、少年の場合は、ごく軽微な事件を除き、まず家庭裁判所が少年自身のことを含めて調査・判断するという点が大きな違いです。
3. 家庭裁判所調査官による調査(少年の背景を探るプロセス)
家庭裁判所に事件が送られると、家庭裁判所調査官(ちょうさかん)という専門家が、少年やご家族、学校の先生などから話を聞き、事件のことだけでなく、少年の性格、生育歴、家庭環境、交友関係、事件に至った原因・背景などを詳しく調査します。
この調査官による調査は、その後の裁判官の判断に大きな影響を与える、少年事件手続きにおける非常に重要なプロセスです。調査官は、調査結果を報告書にまとめ、裁判官に提出します。
4. 少年鑑別所での調査(観護措置)
裁判官は、調査官の調査と並行して、あるいはその結果を踏まえ、少年を少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)に収容して、心身の状態や行動を詳しく観察・調査する必要があると判断することがあります。
これを観護措置(かんごそち)といい、期間は通常4週間程度(延長されることもあります)です。 鑑別所は刑務所や少年院とは異なり、少年の資質を理解するための専門的な調査(心理テストなど)を行う場所であり、懲罰施設ではありません。しかし、社会から切り離され身体拘束が続くことには変わりありません。
5. 少年審判(非公開での手続)
調査官の調査や鑑別所の結果などを踏まえ、裁判官は少年審判(しょうねんしんぱん)を開くかどうかを決定します。
審判が開かれる場合、それは非公開で行われます。成人の刑事裁判のように傍聴人がいることはなく、検察官も原則として立ち会いません(重大事件等を除く)。
審判には、裁判官、調査官、少年本人、保護者(ご両親など)、そして弁護士(付添人:つきそいにん)が出席します。
審判は、一方的に処分を決める場ではなく、裁判官が少年に語りかけ、非行に至った原因や反省状況、今後の生活について、関係者が一体となって話し合い、少年の立ち直りのために何が最善かを考える場という性格が強いです。
6. 審判での決定(保護処分など)
- 審判不開始:調査の結果、審判を開くまでもないと判断される場合。
- 不処分:審判を開いた結果、保護処分にする必要はないと判断される場合。
- 保護観察(ほごかんさつ):最も一般的な保護処分。家庭で生活しながら、保護観察官や保護司(地域のボランティア)の指導・監督を受け、更生を目指します。
- 児童自立支援施設等送致:比較的年齢の低い少年が、生活指導等を受ける施設に送られます。
- 少年院送致(しょうねんいんそうち):非行の程度が重い、または保護観察では更生が難しいと判断された場合に、少年院で矯正教育を受けます。少年院は懲役刑とは異なり、あくまで教育・更生のための施設です。
- 検察官送致(逆送:ぎゃくそう):例外的に、殺人などの重大事件で、刑事罰を科すのが相当と判断された場合(原則16歳以上)、事件が検察官に送り返され、成人と同様の刑事裁判を受けることもあります。
弁護士(付添人)の役割

少年事件において、弁護士は「付添人(つきそいにん)」として活動します。付添人は、単に少年の権利を守るだけでなく、少年が自らの問題と向き合い、反省を深め、更生していくプロセスをサポートするという、教育的な役割も担います。
具体的には、以下のような活動を行います。
- 逮捕・勾留された場合の早期釈放活動
- 取調べへの対応アドバイス
- 家庭裁判所調査官との面談、意見交換
- 少年鑑別所への送致(観護措置)を回避するための活動
- 被害者との示談交渉
- 家庭や交友関係など更生に向けた少年の環境調整
- 審判への出席、少年に有利な意見・証拠の提出
- 少年やご家族への精神的なサポート
早期に弁護士(付添人)に相談する重要性
お子様が事件に関与した場合、できる限り早い段階で、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼(付添人選任)することが非常に重要です。
- 手続きが分からない不安の解消:複雑な手続きの流れや、ご家族としてどう対応すべきか、具体的にアドバイスを受けられます。
- 不利な状況の回避:逮捕・勾留や鑑別所送致といった身体拘束を回避・短縮できる可能性が高まります。
- 調査官への働きかけ:調査官の調査段階で、少年にとって有利な事情や更生に向けた取り組みを効果的に伝えることができます。
- 審判への万全な準備:審判で裁判官に良い心証を与え、少年院送致などの重い処分を回避し、保護観察など社会内での更生を目指すための準備を十分に行えます。
- 被害者対応:被害者がいる事件では、早期の謝罪や示談が、処分を軽くする上で極めて重要です。
お子様の未来のために
少年事件の手続きは、お子様の将来にとって大きな分岐点となります。ご家族だけで抱え込まず、また学校や警察の言うことだけを鵜呑みにせず、必ず少年事件の経験豊富な弁護士(付添人)にご相談ください。
当事務所では、少年事件に関するご相談を受け付けております。お子様の更生と明るい未来のために、私たちが法的な専門知識と経験をもって、全力でサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。